
キャベツ栽培で発生する病気と害虫を写真付きで一覧にまとめました。
病害虫の詳細ページでは、効果的な防除方法や予防策なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
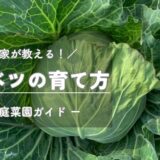 キャベツの育て方と栽培のコツ
キャベツの育て方と栽培のコツ 病気
キャベツに発生しやすい代表的な病気。
萎黄病
カビによる土壌病害で、連作すると発生しやすくなります。
葉の片側が葉脈に沿って網目状に黄化、やがて奇形化し、全体がしおれていきます。
菌核病(きんかくびょう)

白い綿状のカビに覆われ、やがて表面にネズミの糞のような黒い塊(菌核)ができます。
黒腐病

葉の縁から不整形〜V字型で黄色い病斑が広がります。
軟腐病(なんぷびょう)

根こぶ病

茎葉がしおれては回復を繰り返し、根に大小のこぶができます。
その他の病気
害虫
キャベツに発生しやすい代表的な害虫。
アブラムシ
体長1〜2mmほどの小さな虫が葉裏に群棲して吸汁加害します。
主に、白い粉で覆われているような「ダイコンアブラムシ」、赤褐色または緑色で透明感がある「モモアカアブラムシ」。
アオムシ(モンシロチョウ)


緑色の細かい毛がうっすらと生えた小さなイモムシが、葉を食害します。
コナガ

タマナギンウワバ

シャクトリムシのように歩く、緑色をしたイモムシ状の幼虫(ヤガ類)が、葉を食害します。
ネキリムシ


体長4cmほどのイモムシ状の幼虫が、地ぎわで苗を噛み切ります。
ハモグリバエ

乳白色の幼虫が葉肉の中から葉を食害し、葉の表面に絵を描いたような白い筋状の食痕を残します。
ハイマダラノメイガ(芯食い虫)
イモムシ状の幼虫が生長点付近の若い芽や葉を食害します。
被害に遭って生長点を食べられた場合でも、出てきたわき芽を1つだけ残して育てることで、それが育って結球キャベツを収穫することが可能です。
ハスモンヨトウ


夜間にイモムシ状の幼虫が葉を食害します。



