野菜の栽培・ガーデニング等で用いられる用語集です。
随時、追記していきます。
野菜栽培に関する用語
ア行
IPM(総合的有害生物管理)
農薬だけに頼らず、利用可能な全ての防除技術(耕種的防除、物理的防除、生物的防除、化学的防除)を利用し、経済性を考慮しつつ、適切な手段を総合的に講じる防除手法。
 病害虫対策の基本
病害虫対策の基本 赤玉土(あかだまつち)
赤土を乾燥させて、大中小の粒にふるい分けたもの。通気性、保水性が良い。
アレロパシー
植物が放出する化学物質が、他の植物に何らかの影響を与えることで、植物の生育を助けたり抑制したりする作用のこと。日本語では「他感作用」と言う。
あんどん仕立て
鉢に数本の支柱をたて、まわりを紐や輪で囲った中で、植物を絡ませて育てるつくり方。
EC
EC(電気伝導度)とは、土壌中にある物質のイオン濃度の総量。
チッ素などの肥料成分はイオン化された状態で植物に吸収されるため、ECは土壌中の養分(肥料分)の多さを表す。
一番花(いちばんばな・いちばんか)
株の中でいちばん最初に咲いた花。
一番果(いちばんか)
開花後についた最初の実。
ウイルスフリー苗
ウイルスに感染しにくい植物の芽の先端部分を培養させて作った、ウイルスに感染していない苗。
作物本来の能力を発揮し、高品質・多収穫に繋がる。
永年性作物(えいねんせいさくもつ)
一度植えておくと、長い間収穫できる作物。
液肥(えきひ)
液体肥料のこと。即効性があるため、追肥に利用する。
栄養成長(えいようせいちょう)
自らの体を作る個体維持のための成長(葉茎や根の成長)(⇄ 生殖成長)
栄養繁殖(えいようはんしょく)
種子によらず個体数を増やすこと。
F1種子(エフワンしゅし)
異なる性質の2つの原種を交配してできた種子で、両親よりも優れた性質を有する。
尚、F1種子から採った種子を利用しても品種の特性は発現しない。そのため、毎年種子を購入する必要がある。
晩生(おくて・ばんせい)
作物や果物で、おそく成熟する品種(⇄ 早生)
親づる・小づる
つる性の植物ではじめの発芽から伸びて主計となるのが「親づる」。
親づると葉の間から出たわき芽が伸びたものが「小づる」。
お礼肥(おれいごえ)
収穫後、疲労した株を元気にするために肥料を施すこと。
カ行
塊茎(かいけい)
地下茎(地中の茎)の先が養分を蓄えて、塊状に肥大したもの。ジャガイモ、サトイモなど。
塊根(かいこん)
根が塊状に肥大して、養分を蓄えているもの。サツマイモなど。
隔年結果(かくねんけっか)
果樹で、よく実がつく表年(なり年)と実がつかない裏年が1年おきに交互に現れること。実を多くつけた枝には、翌年に花芽が作られにくいという性質から起こる現象。
柑橘、リンゴ、柿、栗で多く発生する。
過繁茂(かはんも)
植物の枝葉が過剰に茂りすぎた状態のこと。窒素肥料や土壌水分の過剰で発生しやすい。
これにより、風通しや日当たりが悪化し、病害虫の発生、着果不良、果実の肥大不良、結球の阻害などの問題が起こる。
株分け(かぶわけ)
大きく成長した株をいくつかに分けること。
過密になった株を若返らせたり、株を増やすために行う。
花房(かぼう)
花蕾(からい)
花のつぼみのこと。ブロッコリーやカリフラワーはこれを収穫する。
植物の茎の先端(頂部)にできる花蕾を「頂花蕾(ちょうからい)」、主茎のわきから伸びる側枝につく小さめの花蕾を「側花蕾(そくからい)」という。
仮支柱(かりしちゅう)
苗木や若い植物を植えた直後に、一時的に支えるための支柱。苗がまだ根付いておらず、風や雨で倒れたり、茎が曲がったりするのを防ぐために設置する。
苗より少し高めの竹や細い園芸用支柱を用い、苗から5〜10cmほど離れた位置に斜めに挿し、8の字結びで緩めに固定する。
感光性(かんこうせい)
一定期間連続する1日の長さによって、植物が栄養成長から生殖成長へ転換する性質のこと。
寒締め(かんじめ)
野菜を冷たい空気にさらすこと。
寒さに耐えるために自ら葉の水分を減らし、糖を増加させるため甘みが増します。葉は厚く、姿は開張型になります。
好光性種子(こうこうせいしゅし)/嫌光性種子(けんこうせいしゅし)
「好光性種子(又は光発芽種子)」は、種が発芽するときに光があった方が発芽が促進される種。そのため、種まきの際の覆土は薄くする。
反対に光に当たると発芽が抑制される種を「嫌光性種子(又は暗発芽種子)」と呼ぶ。
緩効性肥料(かんこうせいひりょう)
施してから穏やかに効果を現し、長期にわたり肥効が持続する肥料。
間作(かんさく)
畝の間や株と株の間に、他の作物を栽培すること。
休眠(きゅうみん)
種、球根、苗などが、生育に適さない時期を越すために、活動を一時的に休むこと。
切り戻し
茎や枝を短く切り詰めること。
クラウン
茎と根の境界部のこと。茎の基部とそこから発生している根の基部をひとまとめにしてクラウンと呼ぶ。
イチゴでは、株元の部分を指すこともある。
 イチゴ(苺)の育て方と栽培のコツ【露地栽培】
イチゴ(苺)の育て方と栽培のコツ【露地栽培】 混作(こんさく)
同じ耕地に2種以上の作物を同時に栽培すること。
サ行
催芽(さいが)
発芽を良くするために、種をまく前に水分や温度を最適にする、種子を傷つけるなどの処理をすること。
在来種(ざいらいしゅ)
昔からその土地で作られてきた固定種の野菜。
CEC
CEC(塩基置換容量)は、土が肥料を吸着できる能力(保肥力)のこと。
土壌はマイナスイオン、肥料の成分(NH4+、Ca2+、Mg2+など)はプラスイオンに覆われているので、土壌は成分を吸着して蓄える。
この吸着できる最大量がCEC(塩基置換容量)。
C/N比
C/N比(炭素率)とは、有機物などに含まれている炭素(C)量と窒素(N)量の比率。
ある有機物に炭素100g、窒素10gが含まれている場合、この有機物のC/N比は10となる。
C/N比が小さいほど窒素を多く含んでおり、肥効の即効性が高い。
- バーク(樹皮): 100〜1300
- イネわら:60
- 米ぬか:23
- 牛糞:16
- 鶏糞:7
自家受粉(じかじゅふん)・他家受粉(たかじゅふん)
同じ花、または同じ株の花で受粉することを「自家受粉」。
異なる株の花粉で受粉することを「他家受粉」。
雌雄異花(しゆういか)・雌雄同花(しゆうどうか)
一つの花に雄しべまたは雌しべどちらかしかない花を「雌雄異花」。
一つの花に雄しべと雌しべの両方を持つ花を「雌雄同花」。
周年栽培(しゅうねんさいばい)
作型を組み合わせることで、作物のある一つの品目を一年中栽培すること。
主茎(しゅけい)・主枝(しゅし)
植物の成長の中心となる主要な茎のこと。
一般的には、種子から発芽した後に最初に伸びる茎であり、そこから側枝(わき芽)が伸びる構造になっている。つる性の植物では親づるという。
受粉・授粉(じゅふん)
「受粉」=「花粉を受ける」。めしべに花粉が付着した”状態”を指す。
「授粉」=「花粉を授ける」。昆虫や人工的にめしべを付着させる”行為”を指す。
春化(しゅんか・バーナリゼーション)
植物が冬の低温状況に一定期間さらされることで、花芽分化して開花が促進されること。
す入り
カブやダイコンなどの根菜類の内部に空洞やスカスカした繊維質ができる現象。
これが起こると、食感がパサパサしてしまい、みずみずしさや甘みが失われてしまう。
生殖成長(せいしょくせいちょう)
子孫を残す種族維持のための成長(花芽形成・開花・結実)(⇄ 栄養成長)
先祖返り(せんぞがえり)
親に現れなかった先祖の遺伝上の性質が、突如として子に現れること。
タ行
太陽熱処理(たいようねつしょり)
太陽熱で地温を上げて、土壌中の病原菌や害虫、雑草などを防除する方法。
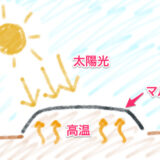 雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる
雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる 単為結果(たんいけっか)
受精しなくても果実ができること。この場合、種はできない。
自然界ではバナナやパイナップルなどで起こり、また、種なしブドウは人工的に誘発したもの。
団粒構造(だんりゅうこうぞう)
個々の土壌粒子が集合して団粒をつくっているもの。
通気性、排水性、保水性にすぐれ,土壌生物の活動も盛んで,植物生育に好ましい土の状態。
 団粒構造の土とは?
団粒構造の土とは? 窒素飢餓(ちっそきが)
作物の生育障害の一つ。
植物の生育に必要な窒素が少ない状況で、有機物を与えすぎることにより生じる。(微生物が大量の窒素を消費してしまい、植物の生育に必要な窒素が不足する。)
C/N比が高い程、窒素飢餓が発生しやすい。
長日植物(ちょうじつしょくぶつ)・短日植物(たんじつしょくぶつ)
「長日植物」とは、ある限界の時間よりも日長が長くなると花芽形成や開花が促進される植物。
「短日植物」とは、ある限界の時間よりも日長が短くなると花芽形成や開花が促進される植物。
接木苗(つぎきなえ)
地下部の根の台木と地上部の茎葉の穂木を接ぎ合わせした苗。
台木に土壌病害に抵抗性を持った植物や、生育旺盛な植物や品種を使うことで、それらの長所を兼ね合わせる。
つるぼけ
葉茎が必要以上に繁茂して、収穫対象である根や果実がよくできない現象。
サツマイモ、キュウリ、スイカなどのつる性作物によくみられることから、こう呼ばれる。
つるぼけの主な原因として、窒素過多(窒素肥料が多すぎる)がある。
摘心(てきしん)
成長点を摘み取ること。
摘心することで伸びる生育をストップさせることができる。また、側枝の発生が促進される。
天地返し(てんちがえし)
土を深く掘って、上層と下層の土を入れ替えること。
厳寒期にこの作業を行い寒気にさらすことで、さらなる効果を得ることも。
 冬の土作り「寒起こし」|土を蘇らせる天地返しの方法
冬の土作り「寒起こし」|土を蘇らせる天地返しの方法 展着材(てんちゃくざい)
農薬を散布するときに、薬剤が水に溶けて植物や病害虫に付着し、効力を持続するように混ぜる補助的薬剤。
 農薬の正しい使い方
農薬の正しい使い方 とう立ち
 野菜のとう立ち(薹立ち・抽苔)について
野菜のとう立ち(薹立ち・抽苔)について 糖度(とうど)
野菜や果物などに含まれる糖の量。
 野菜や果物の甘さを自分で測れる「ハンディ糖度計」
野菜や果物の甘さを自分で測れる「ハンディ糖度計」 徒長(とちょう)
植物が、光不足や通気不良による多湿条件下で弱々しく育つこと。
ナ行
苗床(なえどこ)
野菜や花などの苗(若い植物)を育てるための専用の場所のこと。
種を直接畑にまくのではなく、苗床で発芽・生育させてから植え替えることで、発芽率を高め、苗を丈夫に育てることができる。
 家庭菜園向け「苗作り・育苗」のコツ
家庭菜園向け「苗作り・育苗」のコツ 軟白栽培(なんぱくさいばい)
土を被せるなどして日光を遮り、白くなるように育てること。
ハ行
バイオスティミュラント
植物に対する非生物的ストレスを制御することにより、気候や土壌のコンディションに起因する植物のダメージを軽減し、健全な植物を提供する技術。
農水省が発表した「みどりの食料システム戦略」に「化学農薬の使用低減に向けた技術」として記載されたことで、さらに注目が集まっている。
培養土(ばいようど)
植物の栽培用に複数種類の土や肥料を混ぜ合わせたもの。
花芽分化(はなめぶんか)
 野菜のとう立ち(薹立ち・抽苔)について
野菜のとう立ち(薹立ち・抽苔)について バンカープランツ
病害虫の防除を目的として、害虫の天敵を集めるために育てる植物。
ピートモス
水苔類が長年堆積し、分解してできた有機物の土壌。保水性に富む。
肥料やけ(肥やけ)
肥料を多く施しすぎたり、土壌が乾燥して肥料濃度が濃くなり、根が傷んでしまうこと。
腐食(ふしょく)
土壌中で動植物の遺体が土壌微生物に分解・再合成された暗色無定形(コロイド状)の高分子化合物。
腐食は、無機養分を保持し、土壌の団粒化に役立つなど、作物の生育に重要な役割を果たしている。
 野菜を育てるための土作り
野菜を育てるための土作り BLOF(ブロフ)理論
BLOF = Biological Farming(バイオロジカルファーミング)の略で、作物の植物生理に沿って、科学的・論理的に有機栽培を行う理論。
分げつ・分けつ
イネ科植物やネギなど、根に近い茎の節から枝分かれして株が増えること。
pH(ペーハー)
pH(水素イオン指数)は、土壌の酸性度を示す数値。
0〜14の数値で表される。0(酸性)〜7(中性)〜14(アルカリ性)。
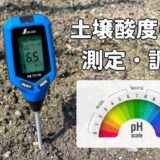 土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について
土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について マ行
間引き
野菜のよい株を残して株間をあけるため、成長の悪い株を抜くこと。
むかご
茎のわき芽が養分を蓄えて肥大した、小さな球根。珠芽(しゅが)とも言う。
株から落ちて発芽するので、繁殖に利用する。(ヤマイモなど)
芽かき
主枝を生長させるため、わき芽を取り除くこと。
木酢液(もくさくえき)
木酢液は、木炭を作る際に出る水蒸気を冷やして得る液体(粗木酢液)を、不純物を除去して蒸留したもの。土壌改良や虫除けなどに使われている。
過去には農薬として登録されていたが現在は失効しており、農薬の効果をうたっての販売は禁止されている。
ヤ行
有機物(ゆうきぶつ)・無機物(むきぶつ)
有機物とは、基本的に生物由来のもので炭素(C)を含む物質のこと。生物体内で作られる炭水化物や脂質、タンパク質など。(二酸化炭素など簡単な元素化合物は無機物に含まれる)
無機物とは、有機物以外の全ての物質。水や金属などのように炭素(C)以外の元素で構成されているもの。
有胚乳種子(ゆうはいにゅうしゅし)/無胚乳種子(むはいにゅうしゅし)
植物の種子は、有胚乳種子と無胚乳種子の2種類に分けられる。
それぞれ養分(発芽に使うエネルギー)を貯蔵している場所が異なり、有胚乳種子は胚乳に、無胚乳種子は子葉に蓄える。
溶液栽培(ようえきさいばい)
土を使用せずに、植物の成長に必要な栄養素を処方した培養液で栽培する方法。
溶脱(ようだつ)
土壌中の物質が、蒸発や降雨などを通じて地下水などに流出すること。
予措(よそ)
種子や球根にあらかじめ病害虫の防除や発芽促進のための処理をすること。
ラ行
リサージェンス
害虫防除のために農薬を散布したにも関わらず、散布前よりもかえって害虫が多くなる現象。
その要因の1つには、農薬散布により対象害虫の天敵が減少してしまうなどがある。
リビングマルチ
野菜を栽培している畑で、同時に緑肥など別の植物を育てて地表を覆うこと。
雑草抑制、地力アップ、土壌流出防止などの効果がある。
鱗茎(りんけい)
葉が養分を蓄えて多肉となって重なり、球形や卵形になったもの。タマネギ、ニンニクなど。
輪作(りんさく)
連作障害を防ぐために、同じ場所に異なる科の野菜を順番に作付けすること。
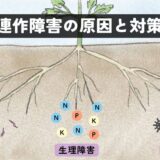 連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について
連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について 露地栽培
ビニールハウスや温室を使わずに、屋外の畑や庭で自然の環境のもとで作物を育てる方法。
ワ行
わき芽
植物の茎と葉の付け根から出てくる新しい芽のこと。側芽ともいう。
わき芽は、そのままにしておくと枝や葉が茂りすぎて、養分が分散してしまい、実のつきが悪くなることがある。そのため、野菜の種類によっては、わき芽を摘み取る「わき芽かき」という作業が必要になる。
早生(わせ)
作物や果物で、早くできる品種(⇄ 晩生)
