
家庭菜園で発生する病害虫は、その原因によって病原菌(カビ・ウイルス・細菌)と害虫(食害性・吸汁性)という5つのタイプに大きく分類できます。
この記事では、それぞれの特徴と基本的な対策を解説します。まずは原因の全体像を掴むことが、効果的な対策への第一歩です。
病原菌
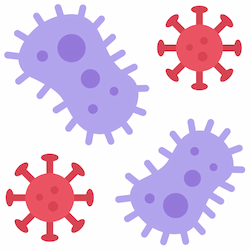
植物に病気をもたらす病原菌の種類は、主に次の3つに分類されます。
カビ(糸状菌)

一般的に「カビ」と呼ばれるものは、菌糸(きんし)という糸状の細胞を伸ばして増殖し、胞子(ほうし)を作って繁殖する「糸状菌(しじょうきん)」を指します。
植物の病気を引き起こす病原菌のうち約7割がこの糸状菌によるものと言われており、最も発生が多い病気の原因です。高温多湿の環境を好み、特にジメジメと蒸し暑い梅雨の時期や、秋の長雨の時期に繁殖しやすくなります。
主な伝染経路
糸状菌は、主に胞子によって伝染します。
風や雨によって飛ばされた胞子が健康な植物に付着し、そこで発芽して植物の体内に菌糸を侵入させます。体内で増殖した菌糸はやがて植物の表面に現れ、新たな胞子を大量に作り、再び風雨によって飛散して感染を広げていきます。
また、病気になった葉や株が土壌に残ることで、そこが次のシーズンの伝染源となる土壌伝染もあります。
病斑(シミやカビ)が目に見える頃には、すでに病気が進行し、次の伝染源になっている状態のため、早期の対策が重要です。
対策方法
糸状菌による病気は、目に見える頃には進行していることが多く、治療も困難です。そのため、特定の病気を治療するよりも、カビが発生しにくい環境を整える「総合的な予防」が重要になります。
- 風通しと日当たりを良くする
密植を避け、適度に整枝・剪定を行い、株全体の風通しと日当たりを確保しましょう。多湿な環境を作らないことが基本です。 - 水はけを改善する
畑の排水性を高め、土壌が過湿にならないように管理します。畝を高くするのも有効です。 - 泥はねを防ぐ
雨水が土を跳ね上げて葉に付着するのを防ぐため、株元に敷き藁やマルチシートを敷くと、胞子の付着リスクを大幅に減らせます。 - 早期発見・早期処分
病気にかかった葉や株は、見つけ次第すぐに取り除き、畑の外で適切に処分して伝染源をなくします。 - 予防的な薬剤散布
発病してからの治療は難しいですが、予防効果のある薬剤を適切な時期に散布することは、発生を抑える上で非常に有効です。
ウイルス

ウイルスは、カビや細菌よりもはるかに小さい病原体で、生物と無生物の中間ともいえる存在です。自分だけでは増殖できず、植物など生きた生物の細胞内に入り込んで初めて増殖し、様々な病気を引き起こします。
ウイルス病は一度感染してしまうと有効な治療薬がないため、感染させないための「予防」が最も重要です。
主な伝染経路
ウイルスの伝染経路は多岐にわたります。
- 昆虫伝染:アブラムシやアザミウマなどの害虫が、ウイルスに感染した植物の汁を吸い、次に健康な植物へ移動することでウイルスを媒介します。
- 接触伝染:ウイルスが付着した手やハサミなどの農具を介して、健康な植物の傷口から感染します。
- 種苗伝染:すでにウイルスに感染している種子や苗から発病します。
- 土壌伝染:病気にかかった植物の残骸(残渣)が土に残り、そこから次の作物へ感染します。
対策方法
ウイルスは電子顕微鏡でなければ見えないほど小さく、症状も似ているため、原因となっているウイルス名を正確に特定するのは困難です。
そのため、特定のウイルスに絞った対策ではなく、以下のような総合的な防除で畑全体への感染リスクを下げることが大切になります。
- ウイルスを媒介するアブラムシなどの害虫を徹底的に駆除する。
- 信頼できる場所から健全な種や苗(無病種苗)を購入する。
- 病気の株を触った後は、手やハサミをこまめに洗浄・消毒する。
- 発病した株は見つけ次第すぐに抜き取り、畑の外で適切に処分する。
細菌

細菌は、ウイルスよりも大きくカビ(糸状菌)よりも小さい、単細胞の微生物です。自然界では物質循環に欠かせない存在ですが、一部の種類は植物に寄生して病気を引き起こします。
水分がある環境で活発に増殖するのが大きな特徴で、高温多湿になる梅雨や夏場に特に発生しやすくなります。
主な伝染経路
細菌の伝染には、「水」が大きく関係しています。
雨水の跳ね返りや水やり(潅水)によって土中の細菌が植物に付着し、害虫による食害痕や作業時についた小さな傷、葉の裏にある気孔などから体内に侵入します。
一度侵入すると、細胞分裂によって爆発的に増殖し、短期間で発病に至るのが特徴です。特に、水はけが悪く、雨が降った後に長時間水がたまるような場所では被害が広がりやすくなります。
対策方法
細菌病も、一度発病すると治療が困難です。そのため、細菌が活動しにくい環境を整え、侵入経路を断つ「予防」が基本となります。
- 水はけを良くして多湿な環境を避ける。
畝を高くしたり、過度な水やりを控えたりして土壌の過湿を防ぎます。 - マルチングで泥はねを防ぎ、株を傷つけない。
泥はねは主要な感染源です。また、作業時に茎葉を傷つけないよう注意します。 - 発病した株はすぐに抜き取り、畑の外で処分する。
伝染力が強いため、見つけ次第、周りの土を含めて速やかに処分します。 - 登録のある薬剤で予防する。
発生が予想される場合は、細菌病に効果のある銅剤などを適切に散布します。
害虫の種類
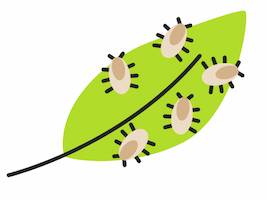
害虫は食害性害虫と吸汁性害虫の2つに分類されます。
食害性害虫

食害性害虫とは、その名の通り、植物の葉、茎、花、果実、根などを直接かじって食べる害虫の総称です。
葉に穴が開く、葉脈だけが残される、新芽が食べられるといった被害が目に見えて分かりやすいのが特徴です。
被害が直接、作物の生育不良や収量の低下、見た目の悪化につながるため、早期の発見と対策が重要になります。特に、気温が上がる夏場は多くの害虫の活動が最も活発になる時期です。
主な種類
非常に多くの種類が存在しますが、畑でよく見られる代表的なものは以下の通りです。
- イモムシ・ケムシ類(チョウやガの幼虫)
アブラナ科につく「アオムシ」や、夜間に活動し多くの作物を食害する「ヨトウムシ」、ダイコンやカブの葉を食べる「コナガ」の幼虫などが代表です。 - 甲虫類
幼虫は根を、成虫は葉や花を食害する「コガネムシ」や、ウリ科の葉を好む「ウリハムシ」、カブやハクサイの葉に小さな穴をたくさん開ける「キスジノミハムシ」などがいます。 - その他の害虫
大群で飛来し葉を食い荒らす「バッタ類」や、湿った環境を好み、夜間に葉や柔らかい果実を食べる「ナメクジ」などもこのタイプに含まれます。
対策方法
食害性害虫の対策は、成虫を畑に入れない「予防」と、発生してしまった虫を駆除する「対処」の両面から行います。
- 防虫ネットや寒冷紗で物理的に防ぐ。
成虫の飛来や産卵を防ぐ最も基本的で効果的な方法です。(物理的防除) - 見つけ次第、手で捕殺する。
被害の初期段階では、手で取り除くのが確実で迅速な対策になります。 - 雑草や作物の残渣を適切に管理する。
害虫の隠れ家や発生源をなくし、畑を清潔に保ちます。 - 対象の害虫に登録のある薬剤を適切に使用する。
多発して手での駆除が追いつかない場合は、BT剤(生物農薬)なども含め、適切な薬剤の使用を検討します。
吸汁性害虫

吸汁性害虫とは、細長い針のような口(口針)を植物の茎や葉に突き刺し、養分である汁を吸う害虫の総称です。
葉に穴が開くことはありませんが、汁を吸われることで植物の生育が悪くなったり、葉が縮れたり、斑点が出て変色したりします。また、害虫の排泄物にカビが繁殖する「すす病」を誘発することもあります。
しかし、吸汁性害虫の最も厄介な点は、植物から植物へと移動する際に「ウイルス病」を媒介することです。目に見える被害が小さいからと放置すると、畑全体に病気が蔓延する原因になりかねません。
主な種類
小さくて見つけにくい種類が多く、気づいた時には大量発生していることも少なくありません。
- アブラムシ類
新芽や若葉に群生し、急速に増殖します。多くのウイルス病を媒介する代表的な害虫です。 - ハダニ類
非常に小さく、葉の裏に寄生します。被害が進むと葉にかすり状の白い斑点が無数に現れます。高温で乾燥した環境を好みます。 - アザミウマ類(スリップス)
花や新芽に潜り込み、汁を吸います。被害を受けた部分は白っぽく変色したり、奇形になったりします。これもウイルス病の媒介者として知られます。 - カメムシ類
果実や豆類の汁を吸い、商品を傷物にします。独特の悪臭を放つことでも知られています。 - コナジラミ類
その名の通り白い小さな虫で、葉の裏に密集します。株を揺すると一斉に飛び立つのが特徴です。
対策方法
吸汁性害虫はウイルス病を運んでくるため、食害性害虫以上に「畑に入れない」という予防の意識が重要になります。



