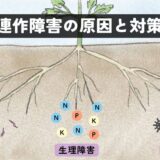野菜や果物の分類には、私たちが普段食べている部分(食用部位)による分け方だけでなく、植物学的な成り立ちや栽培上の都合など、さまざまな視点が存在します。
これらの分類法を知ることで、それぞれの野菜や果物が持つ本来の姿が見えてきて、日々の料理や家庭菜園、お店での選び方がもっと面白くなるはず。
このページでは、「野菜と果物の分類」について、分かりやすく解説していきます。
野菜の分類
食用部位による分類
野菜の食べる部位により、「葉菜類」「果菜類」「根菜類」の3つに分類されます。
植物学的な分類
生物学的な特徴に基づく最も基本的な分類です。
栽培する上で、同じ科の野菜は似た性質を持つことが多く、連作障害の対策にも役立ちます。
その他の分類
農業・園芸分野での分類
利用目的などから大きく次のように分類されます。
- 普通作物(食用作物)・・・米、麦、とうもろこし、いも類など、主に主食や主要なエネルギー源となる作物
- 園芸作物・・・集約的な管理を必要とし、鮮度や品質が重視される作物群
- 工芸作物・・・お茶、タバコ、菜種、い草など、加工して利用されることを目的とした作物
- 飼料作物・・・家畜の飼料(エサ)として栽培される作物
園芸作物はさらに次のように細分化されます。
- 野菜・・・主に畑で栽培される草本植物で、その一部を副食として利用するもの
- 果樹・・・長年にわたって栽培される木本植物で、主にその果実を食用とするもの
- 花卉・・・観賞を目的として栽培される植物
品種(熟期)による分類
同じ種類の野菜でも、品種によって種まきから収穫までのスピードが異なります。この収穫時期の早さや遅さで分類するのが「熟期」による分け方です。
生育の早いものを早生(わせ)、遅いものを晩生(おくて)、中間を中手(なかて)といいます。
栄養価による分類
- 緑黄色野菜・・・緑や赤や黄色が濃い野菜で、特にβ-カロテンを豊富に含んでいる
- 淡色野菜・・・緑黄色野菜以外の野菜で、切ったとき中が白っぽいもの
生育に適した温度による分類
- 高温性野菜(夏野菜)・・・生育適温が比較的高く、暑さに強い野菜(トマト、ナス、キュウリ など)
- 冷涼性野菜(冬野菜)・・・生育適温が比較的低く、涼しい気候を好む野菜(キャベツ、ほうれん草、大根 など)
来歴による分類
- 在来種(伝統野菜)・・・ある地域で古くから栽培され、その土地の風土に適応した品種
- 西洋野菜・・・ヨーロッパなどから導入された野菜
- 中国野菜・・・中国から導入された野菜
栽培場所による分類
- 露地野菜・・・屋外の畑で栽培される野菜
- 施設野菜・・・ビニールハウスや温室などの施設内で栽培される野菜
果樹の分類
木の性質による分類
落葉の有無による分類
- 落葉果樹・・・秋末になると落葉する果樹(リンゴ、ナシ、モモ、ブドウ、クリ など)
- 常緑果樹・・・一年中葉の付いている果樹(柑橘類、ビワ など)
木の形による分類
- 高木性果樹・・・樹高が高くなる果樹(リンゴ、ナシ、モモ、カキ、クリ など)
- 灌木(かんぼく)性果樹・・・樹高が比較的低い果樹(キイチゴ、グミ、ブルーベリー など)
- つる性果樹・・・自立する幹を持たず、つるを伸ばして他のものに絡みつきながら成長する果樹(ブドウ、キウイフルーツ など)
果実の構造による分類
- 仁果(じんか)類・・・花托(かたく)が発達して果実になるもの(リンゴ、ナシ、ビワ など)
- 核果(かくか)類・・・果実の中心に硬い核があるもの(モモ、スモモ、ウメ、サクランボ など)
- 漿果(しょうか)類・・・種子が果肉の中に散らばっているもの(ブドウ、カキ、キウイフルーツ など)
- 柑橘類・・・ミカン科の果樹の総称(ウンシュウミカン、レモン、ユズ など)
- 堅果(けんか)類・・・いわゆるナッツ類(クリ、クルミ など)
その他の分類
受粉の性質による分類
- 自家結実性・・・自分の花粉で実がなる性質。1本でも実をつける。(柑橘類の多く、ビワ、カキ など)
- 自家不和合性・・・自分の花粉では実がなりにくいため、異なる品種の木(受粉樹)を近くに植える必要がある性質(リンゴ、ナシ、ウメ など)
栽培地の気候による分類
- 熱帯果樹・・・年間を通して高温多湿な熱帯地方が原産の果樹(バナナ、パイナップル、マンゴー など)
- 亜熱帯果樹・・・熱帯と温帯の中間に位置する、比較的温暖な亜熱帯地方が原産の果樹(柑橘類の多く、ビワ など)
- 温帯果樹・・・四季の変化がはっきりしている温帯地方が原産の果樹(リンゴ、ナシ、モモ、ブドウ、カキ など)