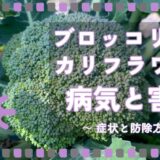ピーマン・トウガラシ類の栽培で発生する病気と害虫を写真付きで一覧にまとめました。
病害虫の詳細ページでは、効果的な防除方法や予防策なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
 ピーマン・パプリカの育て方と栽培のコツ
ピーマン・パプリカの育て方と栽培のコツ  トウガラシ(唐辛子)・シシトウの育て方と栽培のコツ
トウガラシ(唐辛子)・シシトウの育て方と栽培のコツ 病気
ピーマン・トウガラシ類に発生しやすい代表的な病気。
うどんこ病

葉や茎の表面にうどん粉をまぶしたように白いかびが生えます。
青枯病(あおがれびょう)
元気だった株が急にしおれ、青みを残したまま枯れてしまいます。
疫病(えきびょう)
葉に水がしみたような暗緑色の病斑が現れ、裏面には白いカビが発生、やがて枯れます。
ピーマン白斑病

主に葉に発生し、最初は褐色の小斑点を生じ、やがて周縁が濃褐色の病斑になります。
病原菌はトマト斑点病の病原菌と同種で、近くにトマトがあると発生しやすい。
モザイク病
葉に濃淡のモザイク模様が現れ、ひどくなると葉は縮れて奇形化します。
原因ウイルスをアブラムシが媒介します。
その他の病気
害虫
ピーマン・トウガラシ類に発生しやすい代表的な害虫。
アブラムシ

体長1〜2mmの小さな虫が集団で棲みつき、吸汁加害します。
モザイク病のウイルスを媒介するため、注意が必要。
主に、赤褐色または緑色で透明感がある「モモアカアブラムシ」、黄色・緑色・黒色などさまざまな「ワタアブラムシ」。
ホオズキカメムシ


亀のような形をした昆虫が、つぼみや果実を吸汁加害します。
タバコガ

緑色をしたイモムシ状の幼虫が、ピーマンの果実に潜り込んで食害します。
ハスモンヨトウ

イモムシ状の幼虫が、葉肉を裏側から食害します。