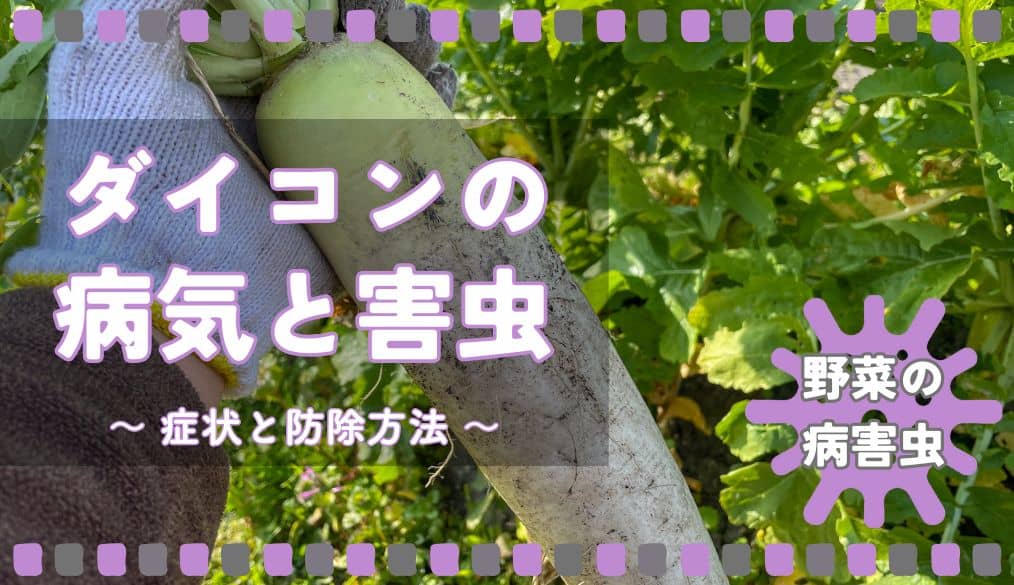
ダイコン(大根)栽培で発生する病気と害虫を写真付きで一覧にまとめました。
病害虫の詳細ページでは、効果的な防除方法や予防策なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
 ダイコン(大根)の育て方と栽培のコツ
ダイコン(大根)の育て方と栽培のコツ 病気
ダイコンに発生しやすい代表的な病気。
萎黄病(いおうびょう)
下葉からしだいに黄化・萎縮・奇形化、やがてしおれていきます。
白さび病

葉裏に乳白色の膨れた斑点ができ、白い粉状の胞子のうができます。
炭疽病
主に葉に灰褐色で円形の病斑ができ、古くなると破れて葉に穴があきます。
軟腐病(なんぷびょう)

組織が水浸状になり、軟化して独特の悪臭を放ち腐敗します。
べと病
葉に黄色の小さい病斑ができ、裏面にすす状のカビが発生します。
モザイク病
葉に濃淡のモザイク模様が現れ、ひどくなると葉は縮れて奇形化します。
原因ウイルスをアブラムシが媒介します。
その他の病気
害虫
ダイコンに発生しやすい代表的な害虫。
アオムシ(モンシロチョウの幼虫)

緑色の細かい毛がうっすらと生えた小さなイモムシが、葉を食害します。
ニセダイコンアブラムシ

カブラハバチ

黒藍色をしたイモムシ状の幼虫が、葉を食害します。
コナガ

ダイコンハムシ


体長1cmに満たない、黒色の幼虫、成虫(丸い形をした甲虫)が、葉を食害します。
ネキリムシ


体長4cmほどのイモムシ状の幼虫が、地ぎわで苗を噛み切ります。
ネグサレセンチュウ
根に寄生し、根を腐らせたり葉を枯らせる土壌病害虫。
ダイコンの肌に黒い斑点を発生させ、品質を落とします。
ヨトウムシ

体長3cmほど、淡緑色をしたイモムシ状の幼虫が、葉を食害します。



