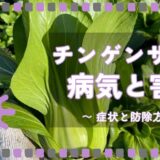トウモロコシ栽培で発生する病気と害虫を写真付きで一覧にまとめました。
病害虫の詳細ページでは、効果的な防除方法や予防策なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
 トウモロコシの育て方と栽培のコツ
トウモロコシの育て方と栽培のコツ 病気
トウモロコシに発生しやすい代表的な病気。
モザイク病
葉に濃淡のモザイク模様が現れ、ひどくなると葉は縮れて奇形化します。
原因ウイルスをアブラムシが媒介します。
その他の病気
| 褐斑病 | 葉に褐色の病斑ができます。 |
害虫
トウモロコシに発生しやすい代表的な害虫。
ムギクビレアブラムシ


体長1〜4mmの小さな虫が集団で棲みつき、吸汁加害します。
モザイク病のウイルスを媒介するため、注意が必要。
アワノメイガ


トウモロコシの大敵「アワノメイガ」。
黄白色でイモムシ状の幼虫が、茎や果実に小さな穴をあけて中に入り込み食害します。