
「カメムシ」は、果実や葉を吸汁して植物に被害を与える害虫です。
本記事では、被害の特徴から生態、効果的な防除方法までを写真付きで解説します。
 病害虫対策の基本
病害虫対策の基本 被害の特徴
カメムシは、群がるように植物のあらゆるところに針状の口を挿して吸汁します。
新芽や花が寄生されると縮んだり奇形となって生育が妨げられます。果実が寄生されると被害を受けた果肉部がスポンジ状になり、そこから腐ってきたり成長が止まり奇形となったりします。
写真は、カメムシに吸汁加害されたミニトマト。


吸汁された果実は見た目が透けたようになり、中身がスポンジ状で触ると柔らかくなっています。また、食べても異臭がします。
豆類もよく被害を受け、サヤが吸汁されると実の入りが悪くなります。
色々なカメムシ






生態
晩秋には家屋の中にもよく飛んできて、触ると悪臭を放ち、「へクサムシ」「ヘコキムシ」などとも呼ばれます。
カメムシの種類は多く、日本だけでも約1000種類以上にのぼります。一般的には1cm前後で緑色や茶色の四角っぽい虫を思い浮かべますが、大きさ・色・形・模様も様々です。
種類によって異なりますが、年1〜3回ほど発生。成虫は、落ち葉や樹皮の下、建物の中に入り込んで壁の隙間などで越冬します。
防除方法
対処法
カメムシは移動性があるため、薬剤の散布時期を逃しやすく対処が困難です。
幼虫や成虫を見つけたらすぐに駆除することが大切。強くつかむと悪臭を放つので、ガムテームなど粘着性のものでくっつけると捕りやすいです。
数が多い場合は捕殺では間に合わないので、薬剤による駆除が簡単で効率的です。
有効な薬剤(農薬)
薬剤防除に有効な農薬には、次のようなものがあります。
「ベニカAスプレー」は、植物を食べる虫や群がる虫をすばやく退治するスプレー式の殺虫剤。ノックダウン効果に優れ、素早い効きめが特徴です。
「ベニカ水溶剤」は、有効成分が植物体内に吸収され効果が持続する浸透移行性の殺虫剤です。植物の汁を吸う害虫はもとより、葉を食害する害虫や甲虫類にも優れた防除効果を発揮します。
予防法
草丈が低いものであれば、防虫ネットを被せておくと防ぐことができます。
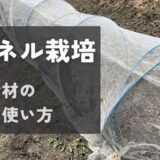 トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方
トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方 また、葉の裏に卵を産み付けられている場合が多いので、見つけたら孵化する前に駆除しておきましょう。

周辺の雑草や落ち葉など、成虫が越冬できる場所を作らないよう、こまめに処理することも大切です。





