
「メイガ」は、植物の茎や果実に入り込んで食害し、生育や収穫に大きな被害を与える蛾の幼虫です。
本記事では、被害の特徴から生態、効果的な防除方法までを写真付きで解説します。
 病害虫対策の基本
病害虫対策の基本 被害の特徴
メイガ類(蛾の一種)の幼虫が植物を食害します。
種類が多く、葉を折り合わせて葉の表面を食害するものや、野菜の葉を食害し芯止まりなどの被害を与えたり、果実に入り込んで食害するものなど多様。
果実や野菜の芯を食べるものは、シンクイムシ(芯喰い虫)とも呼ばれます。
アワノメイガ
トウモロコシの天敵とも言える「アワノメイガ」。


黄白色の幼虫が、茎や果実に潜り込んで実などを食害します。
ウリノメイガ(ワタヘリクロノメイガ)
ウリ科野菜につく「ウリノメイガ」。


緑色の幼虫が葉や果実を食害。中・老齢幼虫になると、葉を綴りあわせて丸め、その中に潜んで葉を食害します。
シロイチモジマダラメイガ
エダマメに必ずというほど発生する「シロイチモジマダラメイガ」。


幼虫がさやに潜り込んで豆(子実)を食害します。
アズキノメイガ(フキノメイガ)

幼虫が茎やサヤに潜り込んで食害します。
アズキ、インゲンマメで発生が多く、他にオクラやナスも加害します。
ワタノメイガ
オクラの葉につく「ワタノメイガ」。


蜘蛛の糸のような粘着性のもので、葉を綴りあわせて丸め、中に潜んで葉を食害します。
ハイマダラノメイガ
アブラナ科野菜に発生。成長点付近の葉を食害するので、生育が極端に悪くなることがあります。
幼虫は「ダイコンシンクイムシ」とも呼ばれます。
ベニフキノメイガ

シソやハーブ類に発生。
葉や枝を糸でつづり合わせて食害します。
シロオビノメイガ
ヒユ科植物、ホウレンソウに発生。
淡緑色の幼虫が葉裏に寄生し、表面だけを薄く残して葉肉を食害します。
生態
種類が多く、生態も様々。
一般的には4月〜10月にかけて年3〜5回の発生。加害場所などで幼虫や蛹の状態で越冬します。
葉裏の葉脈付近に1個ずつ産卵し、孵化した幼虫は葉肉内や葉の上で食害します。
防除方法
対処法
幼虫が茎や果実に入ってしまうと駆除するのは難しく、被害を確認したら早めにその部分ごと切り取ります。
農薬(殺虫剤)を使う場合は、種類に応じて次のようなものがあります。
ウリノメイガには、天然成分で有機JAS規格(オーガニック栽培)にも使える殺虫剤「STゼンターリ顆粒水和剤」などが有効です。天然微生物(B.t.菌)が作る有効成分が、チョウ目害虫に効果をあらわします。
シロイチモジマダラメイガには、「スミチオン乳剤」などが有効です。広範囲の作物に使用でき、幅広い害虫に効果のある代表的な園芸用殺虫剤です。
ハイマダラノメイガやアズキノメイガ(フキノメイガ)には、チョウ目害虫に優れた効果がある「ベニカS乳剤」などが有効です。速効性と持続性があり、害虫を効果的に退治します。
アワノメイガについては、別ページにまとめています。
 アワノメイガ|被害の特徴・生態と防除方法
アワノメイガ|被害の特徴・生態と防除方法 予防法
種まきや定植後から収穫まで、防虫ネットをトンネル掛けして、成虫が飛来し産卵するのを防ぎます。
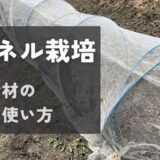 トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方
トンネル栽培に使う被覆資材の種類と使い方 肥料過多や弱った株につきやすいので、施肥は適正量でしっかりとした株を育てましょう。
また、被害が多くなる前に収穫できるよう、早生品種を早めにまくのも1つです。






