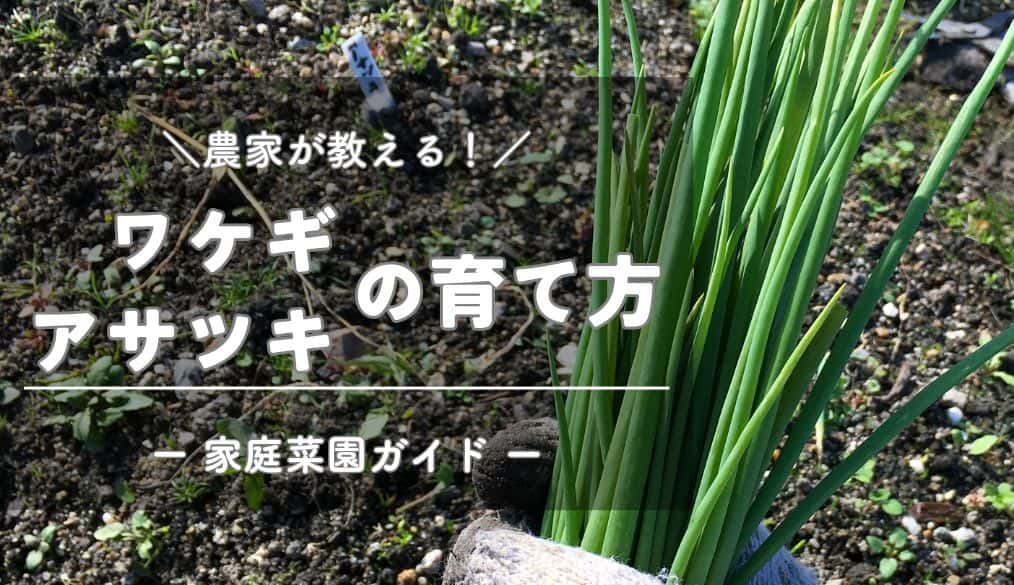
家庭菜園でのワケギ(分葱)・アサツキ(浅葱)の育て方や栽培のコツを農家が分かりやすく解説します。
気になる項目があれば、目次をクリックしてすぐに確認できます。
基本情報

ワケギ(分葱)・アサツキ(浅葱)はネギの仲間ですが、種から育てるネギと違い、種球(球根)を植えて育てます。
分けつ力が旺盛で、繰り返し収穫できるので、小ネギの代わりに重宝します。
収穫期が過ぎて葉が枯れたら、次の年用に種球を採ることもできます。
手間が掛からず栽培も容易なので、プランター栽培にも向いています。ベランダなどで栽培しておくと、欲しい時にすぐに収穫できて便利です。
- 刈り取り収穫後に追肥しておけば、再生した葉を繰り返し収穫できる
- はじめに種球を入手すれば、2年目からは掘り起こした種球を利用可能
栽培カレンダー
ワケギ(分葱)・アサツキ(浅葱)の栽培時期は次のようになります。
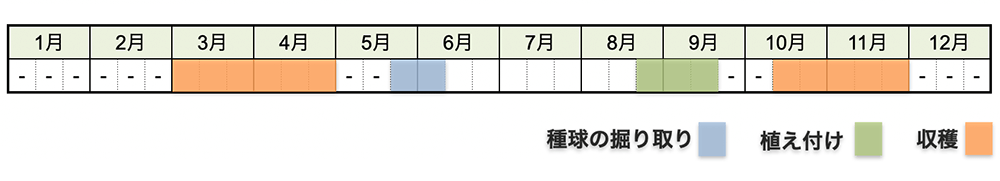
中間地を基準とした目安です。地域や品種によって時期に幅があります。
近年の気候変動による高温や大雨などで、従来の栽培時期が合わないことがあります。状況に応じて、時期をずらす、品種を変えるなどの対応も必要。
8月〜9月頃に植え付け、秋と春の年2回収穫することができます。
また、6月頃に球根を掘り起こして保存しておくことで、2年目からはその種球を利用することができます。
ワケギとアサツキの違い
ワケギ(分葱)
ワケギは、ネギとタマネギの交雑種です。
ネギよりも穏やかな香りと上品な風味が特徴です。
アサツキ(浅葱)
アサツキは、エゾネギの変種。もともとは野草の一種で、山野で自生しています。
ネギ(葱)よりも色が浅いことから、浅葱という名前の由来になっています。
鱗茎ごと食べられ、香りと辛味があって薬味として使われます。↓こんな食べ方も。
 浅葱(あさつき)の美味しい食べ方レシピ
浅葱(あさつき)の美味しい食べ方レシピ 栽培方法
ワケギ(分葱)・アサツキ(浅葱)の栽培は、次のような流れになります。
種球の準備
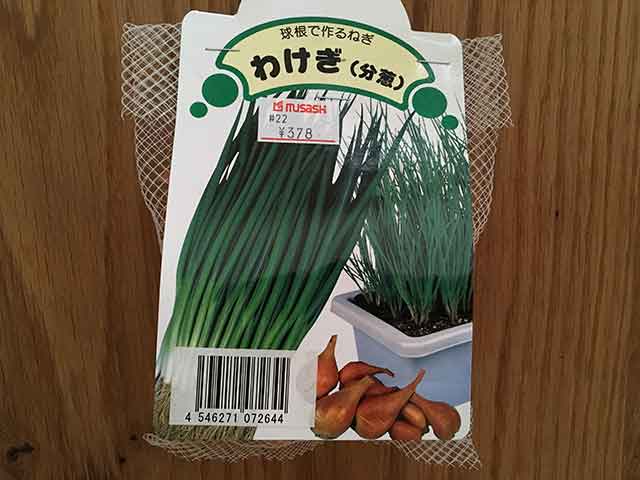
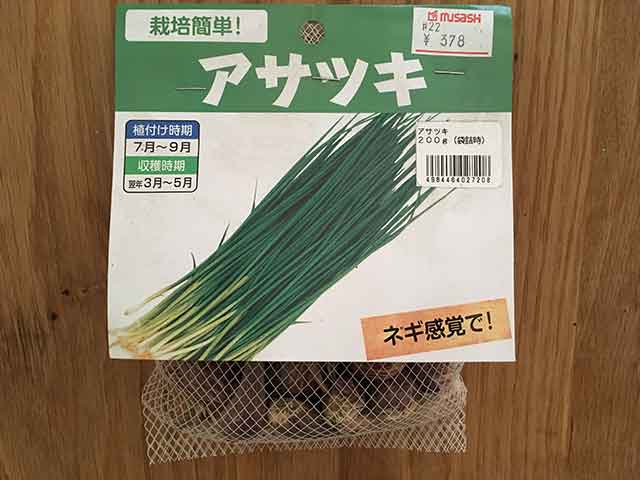
ワケギ・アサツキの種球は、8月頃になると種苗店やホームセンターで販売されます。
前年に栽培して掘り上げ、保存していたものを種球として利用する場合は、小さいものや枯れているものを取り除き、大きくてハリのあるものを選びましょう。
土作り

植え付けまでに「土作り」を済ませておきます。
作物の初期育成に必要な養分を補うため、肥料を施します。
肥料が好きなので、元肥は多めに施しておきます。「ボカシ肥」や「マイガーデンベジフル」のようなバランスのとれた配合肥料がオススメです。
排水性・通気性を確保するため、畝を立てます。
また、マルチングしておくと雑草抑制になり、後々の管理に手間が掛かりません。
その際は、タマネギ用の穴あきマルチ(株間15cm)を利用すると、穴をあける手間が省けて便利です。
 マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント
マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント 土作りのやり方については、こちらの記事で詳しく解説しています。
 野菜を育てるための土作り
野菜を育てるための土作り 植え付け
植えやすいように、種球を1球ずつに分けます。


株間15cm(ワケギ)/株間10cm(アサツキ)で、芽(とがった方)を上にして、1つの穴に2球ずつ植え付けます。


種球を植え付ける深さは、土の表面に種球の先端がやや見える程度の浅植えにします。
追肥・土寄せ
草丈が10〜15cmになったら、条間(植えた列の間)に追肥を施します。

このとき、株元に軽く土寄せをしておきます。
その後の追肥は、収穫した後に行います。
収穫
収穫期は秋と春の2回あります。
秋に草丈20cmになったところで、地際から3cmほど残し、葉だけを切り取って収穫します。



再生力が旺盛で、刈り取った後から新芽が伸びてくるので、同様にして数回収穫することができます。
冬に葉が枯れてきたら収穫期は終わり。そのまま畑に置いておき、春になるとまた新芽が出てくるので、同じように収穫できます。
また、根ごと掘り上げて、卵型に太った根の部分も食べることができます。
種球の掘り上げ
種球を掘り上げて保存することで、次回の栽培に使うことができます。
春の収穫後に株元を残してそのまま生長させ、球根を肥大させます。
5月頃になると株元に球を形成して、葉は枯れて休眠に入ります。5月下旬〜6月上旬頃に球根を掘り上げ、風通しの良い日陰で夏まで貯蔵しておきます。
7月〜8月になると休眠から覚めて芽が伸び始めるので、畑に植え付けて同様の工程を繰り返します。
連作障害とコンパニオンプランツ
連作障害
ワケギ・アサツキは多年草ですが植えっぱなしにはせず、春に種球を掘り出して、夏過ぎに植え直します。
連作障害はほとんどありませんが、病気予防のためにも同じ場所での栽培間隔を1〜2年あけるようにします。
コンパニオンプランツ
違う種類の野菜を混植することで、病害虫を抑えたり生長を助けるといった良い影響が出る「コンパニオンプランツ」。
ネギ(ワケギ・アサツキ)の根には、土壌病害を抑える効果のある拮抗菌が共生しているため、コンパニオンプランツとしての利用もオススメです。
栽培Q&A
プランター「サイズ:幅65cm×奥行20cm×深さ20cm、容量15~20ℓ」に、株間10cmで植え付ければ、12株ほど栽培することができます。
植えっぱなしにすると病気や害虫の被害にあいやすくなります。
また、分球した株が増えて混み合ってくるので、葉が枯れてきたら種球を掘り上げて、植え替えるようにしましょう。
再生力が旺盛で、刈り取り収穫後に追肥しておくと葉が再生するので、繰り返し3〜4回は収穫できます。
ワケギ・アサツキともに、葉の下の白い球根も食べることができます。



