
植物が軟化腐敗して強い悪臭を放つようになる「軟腐病(なんぷびょう)」は、細菌による病気です。
本記事では、症状の見分け方から発生原因、効果的な防除方法までを写真付きで解説します。
 病害虫対策の基本
病害虫対策の基本 被害症状
地ぎわの茎に水浸状の病斑が生じ、だんだん褐色に変わります。やがて軟化腐敗し、強い悪臭を放つようになります。
多くの野菜に発生しますが、中でもキャベツ、ハクサイ、レタスなどの結球野菜に多く出ます。




発生原因と伝染経路
病原菌は、細菌の一種。
土壌中の細菌が植物の傷から侵入。道管部で繁殖し、養水分の通り道を塞いでしまうため、地上部は萎れ、地ぎわ部も腐ってしまいます。
植物でも組織の柔らかいもので発生し、組織が硬くなっている樹木では発生しません。
植物に傷が付いていたり、窒素過多により軟弱に育った場合に、細菌に侵入されやすくなります。
梅雨の終わりや夏の高温多湿時に多く発生します。
防除方法
対処法
細菌性の病気は薬剤が効きにくいので、発生したらすぐに株を抜き取り処分します。
薬剤防除には、有機JAS規格(オーガニック栽培)にも使える殺菌剤「Zボルドー」などに予防効果があります。無機銅剤(塩基性硫酸銅)を主成分とし、糸状菌病害から細菌性病害まで幅広い病害に有効です。
尚、細菌病である軟腐病は、発病後の防除は難しいため、初期発生を見落とさないよう注意し、予防散布を重点に対応しましょう。
予防法
高温多湿で発生しやすいので、水はけの悪い畑なら高畝にし、畝にマルチシートを張ることで、泥はねを防ぐようにしておきます。
 マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント
マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント 連作すると出やすくなるので、輪作や混植、間作を取り入れて菌の密度を減らしましょう。
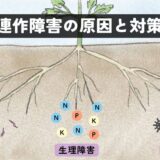 連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について
連作障害の原因と対策、各野菜の輪作年限について 傷口から侵入するため、苗の定植時に根や茎を傷めないように注意し、芽かきなどの作業は乾燥した天気のいい日に行うようにします。また、傷の原因となる、葉を食害する害虫の防除を心がけましょう。
また、窒素過多により軟弱に育った場合に細菌が侵入しやすいので、適切な施肥管理で健康な株を育てましょう。
野菜によっては抵抗性品種があるので、利用することで被害の軽減が可能です。



