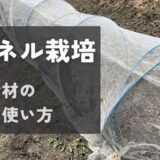「ハムシ(葉虫)」は、植物の葉を食害して生育を妨げる小型の甲虫です。
本記事では、被害の特徴から生態、効果的な防除方法までを写真付きで解説します。
 病害虫対策の基本
病害虫対策の基本
被害の特徴
ハムシは漢字で表現すれば「葉虫」と、文字通り葉を食害して穴だらけにします。
特に新芽の時期への食害は、葉が展開した際に穴や変色、変形となって現れるので品質が損なわれます。
成虫は小さい甲虫で葉を食べ、幼虫は葉を食べるものと根を食べるものがあります。
ウリハムシ、キスジノミハムシの幼虫は、根を食害します。
根を食害されると、日中はしおれ夕方には回復するということを繰り返し、やがて枯れてしまいます。
ハムシの写真
「ダイコンハムシ(ダイコンサルハムシ)」の成虫、幼虫。


体長2〜3mmと小さい「キスジノミハムシ」、アスパラガスにつく「ジュウシホシクビナガハムシ」、ウリ科の野菜につく薄茶色の「ウリハムシ」。



生態
ハムシはコガネムシと同じ甲虫類の仲間です。
種類は多いのですが、寄生する植物が異なり、それぞれ特徴のある色・模様で、体長も2mm〜10mmまでさまざま。
- キスジノミハムシ・・・黒褐色の体で背中に黄色いスジがあり体長2〜3mm
- ダイコンハムシ・・・丸い形をした黒色の甲虫で体長4mmほど
- ジュウシホシクビナガハムシ・・・赤い体に黒い水玉模様の甲虫で体長7mmほど
- ウリハムシ・・・体長7〜8mmで茶色の甲虫
多くは年1回の発生。
幼虫が根を食害する種類は株元の浅い地中に産卵します。種類によって、新芽や葉柄の中に産卵するものや、新葉の上で産卵するものもいます。
多くは成虫のまま、草むらや落葉の下などで越冬します。
防除方法
対処法
見つけしだい手で捕まえて駆除します。
成虫は触るとポロリと落ちて逃げてしまうため、下に払い落としてから掃き取ると捕まえやすいです。
多発すると完全な駆除は難しいため、被害を確認したら早期に防除し、次の発生源を絶つことが大切です。
有効な薬剤(農薬)
薬剤防除に有効な農薬には、次のようなものがあります。
「ベニカ水溶剤」は、有効成分が植物体内に吸収され効果が持続する浸透移行性の殺虫剤です。植物の汁を吸う害虫はもとより、葉を食害する害虫や甲虫類にも優れた防除効果を発揮します。
「ベニカAスプレー」は、植物を食べる虫や群がる虫をすばやく退治するスプレー式の殺虫剤。ノックダウン効果に優れ、素早い効きめが特徴です。
予防法
予防法としては、繁殖力が強いため、何よりも最初の飛来を防ぐのが肝心です。

成虫は反射光を嫌うので、シルバーマルチを敷いたり、銀色の光反射テープを周囲に張ったりすると効果的です。
畝にはマルチングをすることで、幼虫が孵化しづらくなり、被害が抑えられます。
 マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント
マルチシートの種類と効果・失敗しない張り方のポイント
また、ダイコンハムシはニラの香りを嫌う性質があるため、コンパニオンプランツとして近くに植えることで、飛来を防ぐことができます。

ニラの切口から出る液体の匂いを特に嫌がるので、ニラが伸びたら頻繁に刈る、または刈り取ったニラの葉を畝の上に敷くだけでも効果があります。
 コンパニオンプランツの組み合わせと効果
コンパニオンプランツの組み合わせと効果