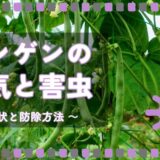イチゴ栽培で発生する病気と害虫を写真付きで一覧にまとめました。
病害虫の詳細ページでは、効果的な防除方法や予防策なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
 イチゴ(苺)の育て方と栽培のコツ【露地栽培】
イチゴ(苺)の育て方と栽培のコツ【露地栽培】 病気
イチゴに発生しやすい代表的な病気。
萎黄病(いおうびょう)
葉が黄色くなってしおれ、3枚の小葉のうち1枚が小型化するのが特徴です。
予防には、連作障害を起こさないようにすることが大切です。
うどんこ病
葉や茎、果実の表面に、薄く白い粉状のカビが発生します。
5月〜6月頃に雨が降らず乾燥が続くと発生しやすくなるので、収穫が始まって土が乾いていたら水やりをしましょう。
炭疽病(たんそびょう)

葉や葉柄、茎に黒褐色のくぼんだような斑点が生じ、ひどくなると株は枯れます。
予防には、畝にマルチシートを敷いて雨水による泥はねを防ぐことが効果的です。
灰色かび病

水浸状の病斑が腐敗を起こし、灰色粉状のカビがつきます。
放置しておくとすぐ伝染するので、被害部分はすぐに取り除いて処分しましょう。
枯れた花や下葉を残したままにしておくと感染しやすくなるので、見つけたら摘み取っておきましょう。
その他の病気
| ウイルス病 | 葉の黄化やねじれ、株全体が萎縮します。原因ウイルスをアブラムシが媒介します。 |
| 輪斑病 | 葉に紫褐色の病斑が生じ、拡大すると中心部が壊死します。 |
害虫
イチゴに発生しやすい代表的な害虫。
アブラムシ

ナメクジ

ハスモンヨトウ

緑色〜茶色でイモムシ状の幼虫が、新葉、蕾、花などを食害します。
その他の害虫
| クルミネグサレセンチュウ | 根に入り込み、根は黒変、株は枯死する。 |