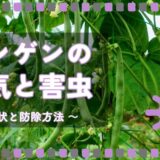エダマメ(枝豆)栽培で発生する病気と害虫を写真付きで一覧にまとめました。
病害虫の詳細ページでは、効果的な防除方法や予防策なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
 エダマメ(枝豆)の育て方と栽培のコツ
エダマメ(枝豆)の育て方と栽培のコツ 病気
エダマメに発生しやすい代表的な病気。
萎凋病(いちょうびょう)
下葉から黄化してしおれ、生育不良となり枯れてしまいます。
白絹病(しらきぬびょう)
地際の茎に白い綿状の菌糸ができます。
酸性土壌で発生しやすいので、土壌の酸度調整を行います。
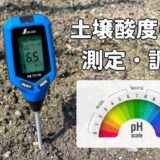 土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について
土壌の酸性度(pH)と測定・調整方法について 発病株はすぐに抜き取り、土を太陽熱殺菌します。
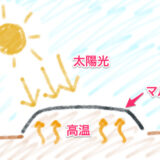 雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる
雑草対策に太陽熱マルチ殺草処理(太陽熱土壌消毒)を試してみる 立枯病
茎の地ぎわ部に縦長の褐変が現れ、やがて茎全体が褐色になって枯れてしまいます。
その他の病気
害虫
エダマメに発生しやすい代表的な害虫。
カメムシ

花が咲き終わってさやができ始める頃から、ホソヘリカメムシ(写真)やイチモンジカメムシなど様々なカメムシがやってきます。
さやが吸汁されると、落果したり、豆が入らなかったり、豆が変形したりします。
さやがついていても、さやや豆が肥大しない場合は、カメムシの被害が疑われます。
コガネムシ

シロイチモジマダラメイガ


エダマメの大敵。
黄緑色をしたイモムシ状の幼虫がさやに潜り込んで豆を食害します。
さやに小さな穴があいている場合は注意。中に幼虫が入り込んでいます。
ダイズサヤムシガ
体長15mmほどのイモムシ状の幼虫が、新葉をつづり合せ葉を食害したり、さやに入り込み豆を食害します。
防虫ネットをトンネル掛けして予防し、見つけたらすぐ取り除きます。
ハダニ

小さい虫が葉裏に群棲して吸汁加害し、葉に白い斑点ができます。
その他の害虫
| ダイズアブラムシ | 小さな虫が葉裏、葉柄、茎の先端やさやに群生して吸汁加害します。ウイルス病を媒介するため注意。 |
| ダイズシストセンチュウ | 根に寄生して養分吸収が阻害され、生育不良になります。 |
| ハスモンヨトウ | 夜間にイモムシ状の幼虫が葉を食害します。 |