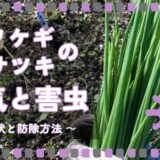我が家で毎年作っている、干し柿レシピを紹介します。
大型品種の「百目柿」を使い、ねっとりと濃厚な甘さに仕上げるのがポイントです。
干し柿に使うのは「渋柿」
柿は大きく「甘柿」と「渋柿」に大別されますが、干し柿に使うのは「渋柿」です。
柿の渋みの正体は「水溶性タンニン」。これが口の中で溶け出すことで渋みを感じます。 甘柿は熟す過程でタンニンが水に溶けない「不溶性」に変化するため、渋みを感じなくなります。一方、渋柿は熟しても水溶性のままなので渋いのです。
しかし、渋柿を干すことで、このタンニンが不溶性に変化し、渋みが抜けて甘くなります。しかも、渋柿は渋みに隠れていますが、実は甘柿よりも糖度が高く、渋柿にするとグッと甘くなります。
ちなみに、甘柿でも干し柿は作れますが、「渋柿ほど糖度が高くならない」「カビが生えやすい」「甘柿なので鳥に突かれやすいと」いう理由から、やはり干し柿には渋柿が使われます。
うちで使うのは「百目柿」
柿には1,000種類以上もの品種があると言われていますが、うちで使うのは「百目柿(ひゃくめがき)」という品種です。

この柿は「不完全渋柿」という種類で、種ができると、その周りだけ渋が抜けて甘くなる性質を持っています。
百目柿は釣鐘のような形でサイズがとても大きいのが特徴。干し柿にするには乾燥に少し時間がかかりますが、その分、濃厚でとろりとした極上の干し柿に仕上がります。
なお、干し柿を作る際は、ヘタの部分にT字の枝を残して収穫するのがポイント。ここに紐を結んで吊るせるようにしておきましょう。

干し柿の作り方
まずは動画で流れを確認。
1. 準備〜吊るす
ヘタの部分を残して皮を剥きます。

50〜60cmほどの紐を準備し、2個で1組になるように紐の両端に結びます。

カビ予防に、沸騰したお湯に柿を10秒間入れて引き上げます。

雨が当たらない軒下の日当たり・風通しの良いところに干します。柿同士がくっつかないようにずらしておきましょう。(雨が当たるとカビが生えてしまうので注意。)

2. 中トロトロで食べ頃
干して2週間ほど。表皮が硬くなってきました。

この頃で水分含有量50%くらい、もう食べることができます。
中トロトロであんぽ柿のようにもの凄く甘い。

3. 揉み込む
干して1ヶ月ほど。黒褐色になってきました。


まだ渋が抜けきっていない中の方まで渋が抜けるよう、指で押すようにして揉み込みます。
4. さらに干してころ柿に
干して1ヶ月半ほど。白い粉をふいてきました。

この白い粉は、柿の糖分が表面に浮き出て結晶になったもの。空気が乾燥して寒い時期になると出やすくなります。
この頃で、水分含有量25-30%くらい。この状態の干し柿は「枯露(ころ)柿」と呼ばれ、羊羹のような食感に。
個人的には「ころ柿」の状態の干し柿が好きで、ワインにとても合うので、お正月のお酒のつまみにしています。

干し柿の焼酎漬け
できた干し柿を焼酎に漬けると、また少し違う味わいの大人のデザートになると聞き、早速やってみました。
熱湯消毒した容器に、ヘタをとった干し柿とホワイトリカーを注ぎ入れ、冷暗所に置くこと3日。



お酒を吸ってふっくらした干し柿は、お酒のアルコールと干し柿の甘味がいい具合に合わさって、ほろ酔い大人の高級デザートといった感じ。
焼酎もいいけど洋酒も合いそう。ラム酒とか良さそうですね。